2017年05月31日
【リサーチ術?】『アナリストが教える リサーチの教科書―――自分でできる情報収集・分析の基本』高辻成彦

アナリストが教える リサーチの教科書―――自分でできる情報収集・分析の基本
【本の概要】
◆今日ご紹介するのは、先日の「未読本・気になる本」の記事でも人気だった1冊。著者の高辻成彦さんは、「経済産業省で経済統計を作成し、現在はアナリストとして業界・企業分析に携わる」という経歴の持ち主です。
アマゾンの内容紹介から。
リサーチを丸投げせずに自前でやるには、何から始めればいいのか?ビジネススクールでは教えてくれない情報の探し方や主なソース、市場規模の見積もり方や比較の仕方など、ビジネスリサーチの基本を学ぶ!
なお、若干ですがKindle版の方がお買い得となっています!
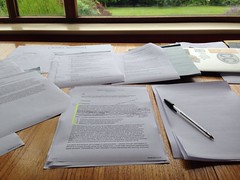
resorting to paper... #research# #proposal / catherinecronin
【ポイント】
■1.そろえるべき4つのツール分析の切り口としては4つあるわけですが、情報が入手できるツールは、バラバラです。特に「Statistics(統計)」と「Share(シェア)」は情報源を見つけるまでは時間がかかりますが、見つけてしまえば分析にはあまり時間を要しません。一方、「Structure(構造)」と「Strategy(戦略)」は業界知識と企業情報がある程度頭に入っていないと分析ができませんので、最も時間がかかります。
ある業界、企業を調べる際に基礎知識がない場合、やみくもに情報を集めすぎても時間がかかってしまいますので、まず次の4つのツールをそろえることを心がけましょう。4つのツールとは、「市販書籍」、「記事情報」、「調査報告書」、「統計」(統計については第3章参照)です。これら4つがそろえば、業界や企業に関する前知識がなくても、ある程度の基礎情報を知ることが可能です。
■2.市場シェア情報の取り方
ここでは、市場シェア情報の取り方について学びましょう。アプローチとしては、次の方法があります。(1)『日経業界地図』を参照する(詳細は本書を)
(2)日経テレコンを使って記事検索する
(3)ネット検索する
(4)矢野経済研究所、富士経済の調査報告書を入手する
(5)業界シェアの調査会社の情報を入手する
(6)『MARKET SHARE REPORTER』の情報を入手する
(7)事業会社のIR情報を入手する
■3.有識者へ取材する
情報収集の初期段階で行う取材活動は、有識者への取材です。有識者とは、専門分野を有する大学教授やコンサルタント、調査会社のリサーチャーなどです。調査の初期段階では、業界の見方そのものがまだ分からない状況にあるため、あらかじめ質問項目を準備した上で有識者の見解を聞くのがいいでしょう。リサーチ分野の全体像をつかむことが目的になりますので、業界構造や主要プレイヤー、市場シェア、最近のトレンドなど、業界のサマリー情報を聞くといいでしょう。有識者への取材は、アウトプットを出す際に説得力を増す材料にもなります。
例えば、コンサルタントがリサーチ報告書をまとめるにあたり、コンサルタント自身の業界に関する見解を述べることはもちろん可能ですが、「〇〇によると〜」など、業界の専門家の見方を付加した方がより説得力が増すことでしょう。また、初期に新聞記事を集めた段階では、新聞記事の内容の真偽の見極めが付きにくいと思います。そういった記事情報の真偽を有識者に質問してみるのもいいでしょう。
■4.市場規模のリサーチの例
手順1:ネット検索するまず、ネット検索をしてみましょう。具体的には、「建設用クレーン 市場規模」のキーワード検索をかけるのがいいでしょう。キーワード検索すると、タダノの決算説明資料が出てきます。そこで、タダノのコーポレートサイトのIR情報ページへいきます。手順2:事業会社のIR情報を確認するタダノのコーポレートサイトのIR情報ページから決算説明資料をチェックしましょう。決算説明資料をみると、世界の建設用クレーンの市場規模の台数、建設用クレーン業界の主要プレイヤーの図が載っています。ここから、台数ベースでの地域別市場規模と主要プレイヤー、タダノの市場シェアが確認できました。(後略)手順3:業界の見通しを確認する次に、建設用クレーン業界の見通しを調べることにしました。前述の決算説明書には、市場規模となる台数実績は掲載されていました。しかし、業界の市場見通しの数値は載っていません。ただし、同社の地域別売上高の計画の数値は載っていました。そこで、地域別の売上高計画の伸び率を参考値としました。(後略)報告A氏は、タダノの決算説明資料に記載の市場規模データと同社の市場シェアデータ、主要プレイヤーの情報、さらには日本建設機械工業会の国内台数実績と新年度の台数見通しを取りまとめ、上司に報告しました。(詳細は本書を)
■5.見解と事実を分ける
リサーチをすると、今後の業界の先行きがどうなるか、といったことや、リサーチした会社の過去の実績の増益・減益要因などについて、状況が分かるようになってくると思います。しかし、その内容が確実な開示情報があるものなのか、自分が調べた結果から類推されることなのか、をきちんと切り分ける必要があります。確実な裏付けとなる情報があるかどうかを調べた上で記述しましょう。例1)2015年度にA社が営業減益になった
→事実
例2)2015年度にA社は、B製品の売上高が減少したため、営業減益となった
→決算短信や決算説明会資料で会社側が触れているなら事実
→何も開示情報から得られなければ、リサーチから推測される見解
例3)2016年度にA社は新製品・Cを売り出すので営業増益に転じるだろう
→見解
【感想】
◆本書を読むにあたって、過去の「情報収集」関係本を振り返ってみたところ、この辺が本書に近いかな、と。
社会人1年目からの「これ調べといて」に困らない情報収集術 (「やるじゃん。」ブックス)
参考記事:【情報収集術】『社会人1年目からの「これ調べといて」に困らない情報収集術』坂口孝則(2016年04月04日)

情報の「捨て方」 知的生産、私の方法 (角川新書)
参考記事:『情報の「捨て方」』が想像以上に凄い件について(2015年05月09日)
ただし、いずれも情報を集めるお話が中心であり、それを加工してビジネスユースのレポートにする、というステージには達していません。
逆に、何らかしらの数値等の「結論」があって、それをグラフや表に加工する、というステージなら、「資料作成術」系の本が多々あるという。
結局本書は、その間に空いた「空白」を埋めてくれる内容なのだと思います。
◆とはいえ、いきなりその「空白」部分だけではなく、上記ポイントの2番目にあるようなデータ元関係も完備。
今回はスペースの関係で、そのポイントの2番目の部分しか挙げていませんが、その分野や用途に応じて、本書にはかなりの数のデータベース等が紹介されています。
さらには、上記ポイントの3番目のように、取材活動についても言及。
その際、割愛してしまったものの、「仮説を持って臨む」ことが大事なようです(詳細は本書を)。
ちなみに、取材でのメモは、高辻さんの場合、Excelを使っているというのも、ユニークだな、と。
◆ただし、本書の一番のキモは、上記ポイントの4番目にあるようなケーススタディでしょう。
下記目次にもあるように、本書の第5章では、こうしたケーススタディで1章を費やしています。
テーマも上記のような「市場規模」だけでなく、「企業業績」の「会社計画との比較」や「競合他社比較」等々。
このポイントの4番目も、スペースの関係で割愛しまくっていますが、本当はもっと詳しいので、詳細は本書にてご確認していただきたいところです。
私自身、集めた情報をどう扱うかが、今ひとつよく分かっていなかったので、この章のコンテンツは助かりました。
◆なお、本書は「ビジネスリサーチ」に関して、広範囲に解説するためか、テイストとしては教科書というか、ビジネススクールのテキストあたりに近い印象です。
高辻さんご自身も、かつてビジネススクールに通われており、グロービスの『MBAシリーズ』を読んでらしたのだとか。
ただし、この「ビジネスリサーチ」だけは、ビジネススクールでも講義がなかったそうで、個々人のスキルに依存するような状況をなんとかすべく、本書を執筆されたとのこと。
それも、専門書としてではなく、こうした一般的な「ビジネス書」として出たがゆえ、仕事で「調べもの」をする方にとって、きっと役に立つと思います。
リサーチ力を高める1冊!

アナリストが教える リサーチの教科書―――自分でできる情報収集・分析の基本
序章 ビジネスリサーチのスキルを身につけよう
第1章 ビジネスリサーチの基礎知識
第2章 業界の基本構造を調べよう
第3章 市場環境・競争環境を調べよう
第4章 補足情報を入手して検証しよう
第5章 リサーチのケーススタディ
第6章 リサーチ結果をまとめよう
第7章 よりレベルアップするために
おわりに
【関連記事】
【情報収集術】『社会人1年目からの「これ調べといて」に困らない情報収集術』坂口孝則(2016年04月04日)『情報の「捨て方」』が想像以上に凄い件について(2015年05月09日)
【知的生産】『仕事ができる人の「情報センス」: 「考える・深める・分かち合う」方法』藤井孝一(2015年09月22日)
意外と知られていない『情報を捨てるセンス 選ぶ技術』のテクニック10選(2014年07月18日)
【情報処理】「情報力」橋本大也(2009年01月19日)
【編集後記】
◆結局当ブログではご紹介できませんでしたが、こちらのセールがいよいよ明日6月1日までとなっています。Amazon.co.jp: 【全品50%OFF】Webデザイン・Web技術書セール(6/1まで): Kindleストア
ジャンル的に興味のある方は、ぜひご確認を!
この記事のカテゴリー:「ビジネススキル」へ
「マインドマップ的読書感想文」のトップへ
スポンサーリンク
この記事へのトラックバックURL
●スパム防止のため、個別記事へのリンクのないトラックバックは受け付けておりません。
●トラックバックは承認後反映されます。
当ブログの一番人気!
Kindle月替わりセール
年間売上ランキング
月別アーカイブ
最近のオススメ
最近の記事
このブログはリンクフリーです






